空の色は何故グラデーション?
風景画を描くのが好きな人へ あなたは水彩で晴天の空をどのように描くだろうか? 技法は個人差があるだろうが、青い絵具を使うことは間違いない。だが空の青は国によっても違うし、季節、時間、見る角度によっても違う。一色の絵具...
水彩画の魅力を伝えるサイト/絵描きとして生きる人のためのサイト
 2.ためになる美術講座
2.ためになる美術講座風景画を描くのが好きな人へ あなたは水彩で晴天の空をどのように描くだろうか? 技法は個人差があるだろうが、青い絵具を使うことは間違いない。だが空の青は国によっても違うし、季節、時間、見る角度によっても違う。一色の絵具...
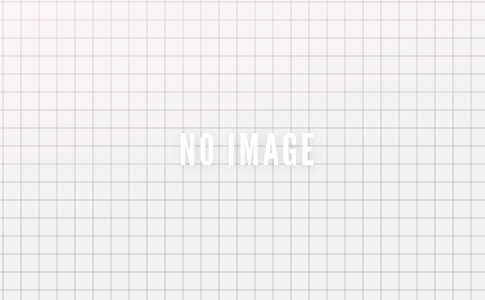 2.ためになる美術講座
2.ためになる美術講座世界遺産 ポン・デュ・ガールを描く 5月初旬。南フランスを旅した。(「絵になる風景を求めて…南フランスを旅する→」参照)今日はその時の水彩画作品「ポン・デュ・ガール」をご紹介しよう。言わずと知れたローマ時代の遺構、世界遺...
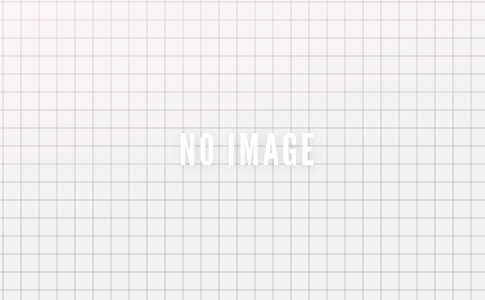 2.ためになる美術講座
2.ためになる美術講座スケッチをしていて思うこと 私は水彩画家であると同時に建築デザイナーである。だからだろうか。旅先で絵を描いていて、いつも思うことがある。スケッチブックに現れる「美しい建物」と「汚れた建物」の違いである。 画家として,風景...
 2.ためになる美術講座
2.ためになる美術講座私の水彩画は建物を描いたものが多い。理由は自然だけを描いた風景画よりも人間臭さ、ドラマを感じるからだ。 今回は上の写真「旧岩﨑邸」に文明開花の頃の建築制作者達のドラマを少し想像してみたい。 岩崎邸とは 久しぶりに訪れた東...
 2.ためになる美術講座
2.ためになる美術講座■美術館二つの顔 以前から見たかったこの美術館、私が惹かれる原因は二つある。一つはもちろん大好きな北斎の作品がたっぷり展示されているから。 もう一つはこの建築の設計者が有名な妹島和世氏であり、そのユニークな空間を自分...