
私は海や山だけを描くことはあまりない。人間の営みが直接感じられないからだ。もちろん例外もある。例えば上の写真を見てほしい。佐渡島の南端にある宿根木(しゅくねぎ)という村(国の重要伝統的建造物群保存地区に認定されている)の海岸から日本海を眺めた風景だ。
日本海の荒い海。岸壁に当たって飛び散る波しぶきが見える。手前の黒くごつごつした岩の間から青い波が浜まで押し寄せてくる。
浜辺の村の生活感に満ちた風景とこの大自然の対比に感動して思わずシャッターを切ったのだ。今回はこの海の風景がテーマである。
①構図をチェックする!
「海」を描くポイントの一つはやはり構図だ。というのは陸の上ならば、例えば遠景に山々があり、中景には林や村落が見え、近景には家屋や庭のディテールが見えるだろう。つまり絵として成立しやすい。
しかし海の風景では基本的には空と海しかない。どうしても構図が単調になりがちだ。
そこで今回のテーマとなる写真を改めてみてほしい。先に述べたように「写真」としては魅力的だと思っている。だが水彩画作品にしようと思うと、実はあまりよろしくない。
私は浜辺の村落と対比する日本海の荒波、波しぶきが描きたかった。だがこの写真をそのまま絵にすると、荒波は遠景に追いやられ、面積の大きい浜辺近くの比較的穏やかなさざ波が主役となってしまう。
そこで構図を操作する。まず今回描くF4号画面の縦横比に合わせた画面をパソコン上で作る。次に先の写真から、岸壁にぶつかる波しぶきを描きたいサイズに拡大して、程よい位置に移動する。
すると当然ながら手前の岩も拡大される。このままでは海の面積に対して大きすぎる。そこで岩の比較的小さい先端部分だけを波とのバランスのよい位置に移動して配置する。こうしてできた新たな構図写真が下図である。
ご覧のように遠景は暗い海、中継は岸壁に当たって砕け散る波しぶき、近景はごつごつとした存在ある岩と青い波だ。構図的には大満足である。
実はこの写真による構図操作はそれなりのデジタルテクニックが必要だ。私は愛用のフォトショップを使用しているが、皆さんもそれなりの画像ソフトに熟練しておくことをお勧めしておく。

②海の遠景と中景を塗る

さて、本来なら無限に広がる海に遠景、中景、近景などという区別は無いだろう。
だが作品とし仕上げるために、今回は意図的にそれを操作した。
まず遠景は日本海らしくグレーで塗る。写真では空と海だけだが、それではさみしいので左端に遠くの陸地を入れることにした。写真と違って絵はこういうところが自由に操作できてよい。
そして中景は岸壁にあたって砕け散る波しぶき…これがこの絵のメインとなる。この部分は波しぶきをひたすら丁寧に描く。細かな飛沫はやはりマスキングインク(詳細はこちら→)と金網、ブラシ(詳細はこちら→)を使うのが一番だ。操作が難しいが、うまく使えばとても便利である。ぜひお試しを。
波をうまく描くこつは細かなしぶきにとらわれず、ある程度大きな波の塊を表現することだ。
波の明暗はコンポーズブルーを中心に、遠景との境目はサップグリーンを混合している。水は多めに、ぼかしながら塗っていく。
③海の近景を塗る
海の近景を描くポイントは2つある。一つは距離感に応じた波の大きさと色を表現すること。もう一つは点景の表現だ。今回は岩の肌合いとそれにかかる波しぶきを表現することである。
中景の波の色は大きく分けて3種類ある。中景の波はコンポーズブルー中心の明るいブルーだった。近景はさらに明暗と海の色がはっきりと分かれる。大きな波しぶきの手前の海は流れが速いので白波が多い。海の色はエメラルドグリーンに近い。
その手前は緑がかった水色。そして岩にぶつかる波は濃いブルーの波である。
白波の部分を残しつつ水を多めに含んだ筆でぼかしながらそれぞれの波を塗っていこう。

仕上げ
ブラシと金網で散らしたマスキングインクをはがすと、いい具合に波しぶきが現れる。「紙の白」はほかの部分よりも圧倒的に白い。周囲の波の色となじませる部分は水だけの筆でこすり、波の色を強調する部分は鮮やかな色をすぐ隣に置いてやる。最後に岩の一番暗い部分を強調して画面を引き締める。
これで完成だ(下図)。

P.S.
水彩画のテクニックについて知りたい方はカテゴリ「絵画上達法→」を参照してほしい。
スケッチ旅の記事に興味のある方は「スケッチの旅海外編→」「スケッチの旅日本編→」を参照してほしい。
この作品を含む私の作品を購入したい方は「水彩STORE/美緑空間→」へどうぞ。








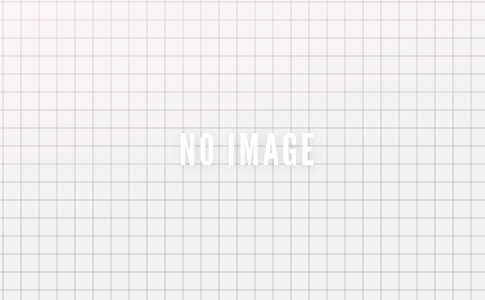


コメントを残す