
京都の風景を描くと言えば、まずは寺社仏閣が頭に浮かぶ。でも京都の魅力はそれだけじゃない。今日はちょっと変わった風景をスケッチしよう。それは京都が東京に首都の座を奪われた頃、つまり明治時時代にさかのぼる。
京の威信を賭けた大事業。それが琵琶湖疏水。
琵琶湖から鴨川まで人工の運河を通すという、当時の技術では困難極まりない工事で、苦労に苦労を重ね、6年の歳月をかけ、明治23年にやっと完成した。その甲斐あって、今も京都市の水道はほとんどこの琵琶湖疎水に頼っているそうだ。
疎水は滋賀県大津市から京都府へ流れ南禅寺に入ると「水路閣」と呼ばれるようになる。
そして今やここは日曜画家が集う人気のスポットになった。
私がスケッチに出かけた時、幸いにも他に絵描きはいないようだった。おかげでよいポジションを奪い合うこともなく、ゆっくり気に入ったアングルを探すことができた。でも改めて考える。
この水路閣がこんなに画家たちの創作意欲を刺激するのは何故だろう?
和風の寺院なかに洋風レンガの建物がある、その組み合わせが面白いからか?
いやスケッチブックを開いた時に感じた高揚感は和と洋の単なる組み合わせの妙だけではないと思うのだ。
本来ここは寺院の宗教空間、境内は「神聖な木立」の連続だ。水路閣はそんな俗世間を寄せ付けないはずの場所に、当時最新の技術である「人工のアーチ」を、やはり最新の材料であるレンガを使い、正確に、木立の間を縫うようにして築かれているのだ。

言ってみれば自然に囲まれた「神域」と人智による「工学」の共存だ
まさにここに私は不思議を感じたのだ。近代国家の首都「東京」に対して「古都の威信」を示したのは意外にも、民衆の信仰心でも、宮廷の文化でもなく近代技術者の心意気だったのだ。
そんな南禅寺はほかの寺院とは一味違う。面白い。絵描きならば、いや絵が好きな人ならば一度は水路閣をスケッチすることをおすすめする。
追伸
いったい誰がこんなものを設計したのかと思われる方のために、ちょっと調べてみた。興味ある方はご覧あれ。
この琵琶湖疏水を設計したのは、田辺朔郎(たなべさくろう)。現在の東京大学工学部にあたる工部大学校を卒業し明治16年、京都府の技術職員となった。
そして若干21歳の時、この琵琶湖疏水の設計者となったのだ。さらにその後蹴上水力発電所を設計し、30歳で東京大学の教授に就任したという。
彼の持って生まれた才能のせいなのか、明治という激動の時代が彼の素質を開花させたのかはわからない。とにかくこの美しい京都の風景を作った天才技術者に感謝したい。
P.S.
このブログの関連記事は以下の通り。興味ある方は参考にしてほしい。
■カテゴリ「スケッチの旅日本編→」
■「ここを描きたい日本の風景!→」
■私のスケッチの実例は「加藤美稲水彩画作品集→」




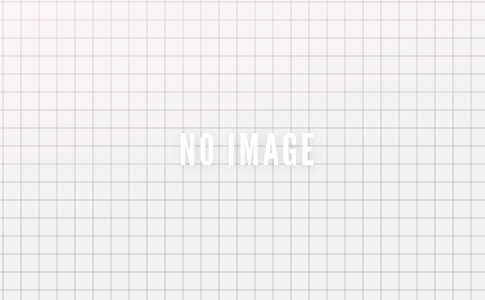







[…] 南禅寺 […]